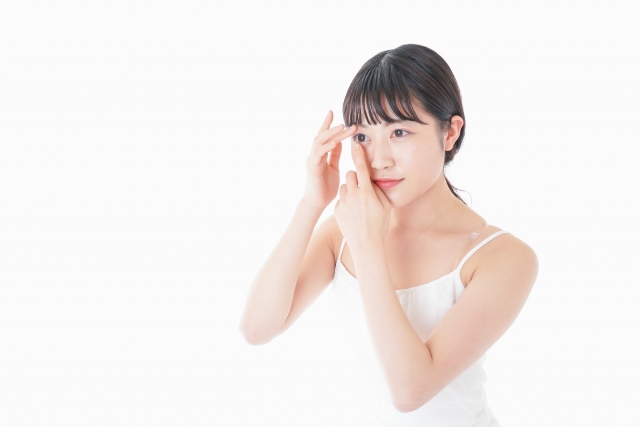2025.06.18
Wednesday
【医師監修】スマホ時代の子どもの目を守る5つの習慣
「気づけば今日もスマホばかり…うちの子の視力、大丈夫かな?」
そう感じたことのある方も多いのではないでしょうか。今、子どもの視力は静かに悪化しています。しかし、近視の進行は日々の生活習慣で大きく変えられます。本記事では、スマホ時代において、親が家庭でできる近視予防の5つの習慣を、眼科専門医の視点からわかりやすく解説します。

目次
子どもの近視が急増している背景
近年、日本をはじめとするアジア諸国では、子どもの近視が急増しています。文部科学省の調査によると、小学生で視力1.0未満の割合はおよそ40%、中学生では60%を超えています。特にここ10年の増加率は顕著で、「スマートフォンやタブレットの普及」「屋外活動時間の減少」「学習時間の長期化」が原因と考えられています。
かつては「本の読みすぎ」「テレビの見すぎ」が問題視されていましたが、今はそれ以上に「画面を顔のすぐ近くで、長時間にわたって見続けること」の影響が懸念されています。
また近視は進行性であり、強度近視になると網膜剥離、緑内障、黄斑変性など、将来的な視力障害リスクも高まります。
しかし希望はあります。国内外の多くの研究から、近視の進行は日常生活のちょっとした習慣で予防・抑制できることが分かっています。これから紹介する5つの習慣は、どれも特別な機器や高額な治療ではなく、親子で少し意識を変えるだけで取り入れられるものです。
習慣①:画面と目の距離を30cm以上離す
近視を防ぐ最も基本的なルールは、「画面と目の距離をしっかり取ること」です。スマートフォンやタブレットを顔のすぐ前で見ると、目の中の毛様体筋という筋肉がずっと緊張状態となり、ピント調節の負担が増します。この状態が続くと、近視進行につながります。
具体的には30cm以上が基準です。子どもには「ひと肘の距離」と教えるとわかりやすいでしょう。
また、目と画面の距離を確保するには姿勢も重要です。テーブルと椅子の高さを見直し、机に向かう時に自然と距離が保たれるようにしましょう。特にタブレットは手に持つとどうしても近づけがちなので、スタンドやブックホルダーの使用がおすすめです。
さらに、画面の明るさや文字の大きさも調整しましょう。明るすぎる画面や小さすぎる文字は目を疲れさせます。最初から「読みにくい」と感じさせない工夫が、距離を保つ意識にもつながります。
習慣②:20-20-20ルールでこまめに目を休ませる
定期的にピント調節のための筋肉を休ませることも重要です。そのためにはアメリカ眼科学会が推奨する「20-20-20ルール」がとても効果的です。
これは20分間近くを見た後は、20フィート(約6m)以上先を、20秒間見るというシンプルなルールです。
画面に集中していると、目はずっと近くにピントを合わせたままになり、疲れやすくなります。子どもは特に集中力が高く、親が声をかけないとずっと画面を見続けてしまう傾向があります。
このルールを習慣化するには、タイマーの使用が有効です。「20分に1回ベルが鳴る→親子で一緒に外を眺める」など、家族で休憩ルーティンを作るのがおすすめです。他にはたとえばYouTubeを見る際、広告が表示されたらスキップせずに遠くを見る、といった工夫も習慣化しやすいです。
また、「遠くを見る時間」が退屈にならないように、ベランダから飛行機を探す、雲の形で遊ぶ、遠くの建物の看板を読むなど、遊びの延長として取り入れると習慣化しやすいです。
習慣③:屋外で1日2時間以上過ごす
近年の研究で、屋外活動が近視進行の予防策につながることが分かっています。
太陽光の中には眼球の過剰な伸び(眼軸延長)を防ぐ働きがある光が含まれているとされています。眼軸が伸びることが近視進行につながるため、このメカニズムは非常に重要です。
理想的な屋外活動時間は1日あたり2時間以上。とはいえ、毎日2時間の外遊びを確保するのは難しいと感じる家庭も多いでしょう。そんな時は、小分けにするのがコツです。
たとえば:
徒歩通学で朝・夕に15分ずつ
帰宅後に近くの公園で30分遊ぶ
休日は1時間の散歩+30分の自転車遊び
など、トータルで2時間を目指せばOKです。
習慣④:就寝1時間前は画面を見せない
夜寝る直前までスマホやタブレットを見ていませんか?
近年の研究で、こうした行動が子どもの睡眠と目の健康に影響を与えることがわかってきています。特に問題となるのがLEDディスプレイから発せられるブルーライトで、これがメラトニン(睡眠ホルモン)の分泌を妨げます。その結果、睡眠の質が低下します。
睡眠は目の疲れを回復させる時間でもあります。眠りが浅いと、目の調節機能が十分に回復できず、翌日の近業作業でさらに疲労が蓄積するという悪循環に陥ります。
そこで、就寝1時間前からデジタルデトックスをおすすめします。
寝る前の1時間は、絵本の読み聞かせ、日記、ぬり絵、ボードゲームなど、目に優しい時間を親子で過ごしてみてください。
また、照明も重要です。就寝前は白色光ではなく、暖色系の間接照明に切り替えることで睡眠の質向上につながります。
習慣⑤:年に1回は眼科で専門的な視力チェックを
「学校検診でA判定だったから大丈夫」──そう思っていませんか?
学校の視力検査では片目ずつの視力低下や不同視、調節異常、斜視などを見逃してしまうことがあります。
また、子どもの視力は日々変化しており、定期的な眼科でのチェックが欠かせません。授業中に見えづらさを自覚していなかったとしても、徐々に近視が進行している可能性があります。
眼科では、屈折度数だけでなく眼軸長を測定することで正確に近視の進行を判定することができます。定期的に検査をすることで進行速度に応じて低濃度アトロピン点眼、多焦点コンタクトレンズ、オルソケラトロジーなどの近視抑制治療の相談も可能です。
よくある質問
Q. ブルーライトカットメガネは意味がありますか?
A. 睡眠の質の改善には一定の効果がある可能性がありますが、近視予防そのもののエビデンスは限定的です。距離・時間・屋外光の方が重要です。
Q. 曇りの日も屋外活動の効果はありますか?
A. あります。曇天でも室内の数倍の光量があり、近視進行抑制に有効です。
Q. オンライン授業やタブレットでの学習時の工夫は?
A. 授業と授業の間など定期的に画面から目を離して遠くを見る休憩時間をとるようにしましょう。
おわりに
スマートフォンもタブレットも、現代の子どもにとって必要不可欠なツールです。完全に制限するのではなく、どう使うかを家庭で整えることが、将来の視力を守る鍵になります。
今日ご紹介した5つの習慣は、家庭で今からできることです。未来の視界を守るために、できることから少しずつ始めていきましょう。
【監修者情報】
⽒名: 山口 雄大
所属: サークル帝塚山眼科 院長
専⾨: 角膜感染症、神経眼科
日本眼科学会認定眼科専門医。
和歌山県立医科大学、済生会有田病院にて勤務。
2023年7月、サークル帝塚山眼科を開設し、院長として診療を行う。
眼科医のための情報サイト「眼科医ぐちょぽいのオンライン勉強会」を運営。
日本眼科学会、日本眼科医会、眼感染症学会、神経眼科学会に所属。