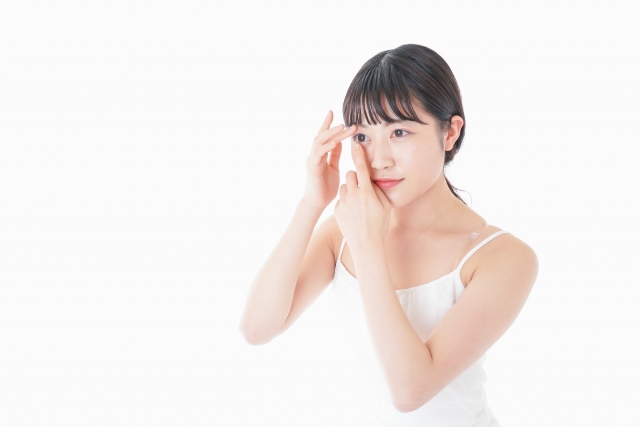2025.06.02
Monday
子どもの近視は防げる? 近視進行の原因と最新治療法
【医師監修】
「学校の視力検査で C 判定だった」「テレビを見る時に目を細めている」──こんな場面に心当たりはありませんか?

小学生の4人に1人が近視と言われる現代、低年齢化が加速しています。しかし、近視の進み方は体質だけでは決まりません。生活環境の改善と医学的に実証された対策を組み合わせれば、強度近視になるリスクを大幅に下げられることが数々の研究で示されています。本稿では、近視が進むメカニズムと、家庭でできる予防から最新の近視抑制治療について詳しく解説します。
目次
1.近視進行の原因は「眼球が伸びる」現象
いわゆる「目が良い」というのは遠くにピントが合っている状態です。近視が進行してくるとピントの合う位置がどんどん近くになってきて、眼鏡をかけなければ遠くがぼやけてきます。このピントの距離を決める要素の一つが眼軸長(眼球の長さ)です。身長が伸びるのと同じで眼軸長も成長とともに伸びていきます。ちょうど良い長さで眼軸長の伸びが止まれば良いのですが、近視のお子さんでは過剰に眼軸が伸び続けてしまいます。しかも伸びた眼軸は基本的に元に戻せないため、「どこまで伸びないようにコントロールできるか」が近視進行対策において重要です。
2.子どもの近視が増える3大背景とその対策
近視の原因には「遺伝的要素」と「環境要素」の2種類が存在します。遺伝的要素としては両親の近視の程度が影響しますがこちらは対策することができないため、ここでは主に環境要素について解説します。
■近距離デジタル作業の増加
スマートフォンやタブレットなどのデジタルデバイスを長時間使用することが近視に悪影響を与えていると言われています。特に30 cm未満の近距離で見続けると、ピント調節のための筋肉が緊張し続けることで近視の進行につながります。
対策
「20-20-20ルール」が有効です。これは20分近くを見たら、20秒間、20フィート(約6m)先を見るという方法です。これによりピント調節の筋肉を休めることで近視進行リスクが下がります。
■屋外活動不足
太陽光を浴びる時間が多い子どもでは眼軸が伸びにくくなることが報告されています。逆に家にこもりきりだと太陽光を浴びる時間が少なくなり、デジタルデバイスを使用する時間も長くなりがちなので注意が必要です。新型コロナウイルス感染症が流行して外出控えが起こった時期には世界的に例年よりも子どもたちの近視が進行していたという報告もあります。
対策
1日平均2時間以上太陽光を浴びることで近視進行が起こりづらくなります。まとめてでなくても構いませんので、通学・公園遊び・部活動などをすべて合わせて2時間以上を目指しましょう。
■睡眠と生活リズムの乱れ
夜更かしをすると起きる時間が遅くなることで、デジタルデバイスを使用したり暗いところで読書をしたりする時間が長くなります。また起きる時間が遅くなると太陽光を浴びる時間も減ってしまうことで近視を進行させてしまいやすくなります。
対策
睡眠不足や生活リズムの乱れはホルモンバランスにも悪影響があります。寝る1時間前はデジタルデバイスの使用をやめましょう。また家庭内の照明を夜間は暖色系の間接照明に切り替えることも有効です。早寝早起きの習慣をつくり、きちんと朝食をとるようにしましょう。
3.医学的に効果が確認された治療法
■低濃度アトロピン点眼
就寝前に 1 滴点眼するだけで、近視の進行を抑えることが可能です。濃度によってはまぶしさやピントのぼやけといった副作用が起こる場合があります。
これまでは海外の製品を輸入して使用するしかありませんでしたが、2024年に日本でもリジュセア®点眼(0.025%)が承認されました。詳しくは眼科でご相談ください。
■オルソケラトロジー
夜だけ専用のハードコンタクトレンズをつけて眠り、朝に外すと日中は裸眼で過ごすことができるという治療法です。レンズが寝ている間に角膜の形を変えてくれることで遠くが見えるようになり、眼軸の伸びにもブレーキをかけることができます。眼鏡や昼間のコンタクトを使いたくない、活発に動き回るお子さんに向いています。装着と洗浄を親子で丁寧に行うことが成功のコツです。
■注目の併用療法
マイオピン点眼とオルソケラトロジー治療をどちらも一緒に行うことで、それぞれ単独で行う場合よりも近視進行抑制効果が高いということが国内から報告されています。可能であれば両者を一緒に行うことが有効かもしれません。
これらの治療効果は視力検査だけでなく眼軸長を参考にしながらみていきます。近視が進行している場合は定期的に眼科で検査をして、近視進行速度をチェックしましょう。
4.強い近視がもたらす将来リスク
「少し悪い程度なら眼鏡で矯正すれば大丈夫」と思われがちですが、近視度数が-6.0Dを超える強度近視になると話は別です。強度近視になると以下の病気のリスクが上昇します。
網膜剥離:突然の視野欠損や失明につながる緊急疾患で、場合によっては手術が必要です。近視がきついと正常の5〜10倍の発症リスクになるとも言われています。
近視性黄斑変性:黄斑と呼ばれる網膜の重要な箇所に障害が起こります。眼の中に注射で薬剤を入れる治療が必要になる場合もあります。
緑内障:視野がじわじわ欠ける疾患で、日本人の失明原因第1位です。強度近視では発症リスクが4倍以上という報告もあります。
早発白内障:水晶体の濁りが通常よりも若い年齢から進みやすくなります。
WHOは2050年までに世界人口の半数が近視、そのうち10億人が強度近視に至ると予測しています。子どものうちに眼軸が伸びるのを予防することは、視力だけでなく将来の失明リスクから守ることにつながります。
5.まとめ 〜今日から始める3ステップ〜
・屋外2時間+20–20–20ルールを毎日の習慣に
・半年ごとの眼軸チェックで進行スピードを数値管理
・進行が速い場合は低濃度アトロピンとオルソケラトロジーを検討
早期介入が未来の視力を守ります。親子で協力して、学ぶ・遊ぶ・眠るをバランス良くデザインしましょう。「うちの子も近視かも」と感じたら、眼科で気軽にご相談ください。この記事がご家族の行動変容のヒントになれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。
【監修者情報】
⽒名: 山口 雄大
所属: サークル帝塚山眼科 院長
専⾨: 角膜感染症、神経眼科
日本眼科学会認定眼科専門医。
和歌山県立医科大学、済生会有田病院にて勤務。
2023年7月、サークル帝塚山眼科を開設し、院長として診療を行う。
眼科医のための情報サイト「眼科医ぐちょぽいのオンライン勉強会」を運営。
日本眼科学会、日本眼科医会、眼感染症学会、神経眼科学会に所属。